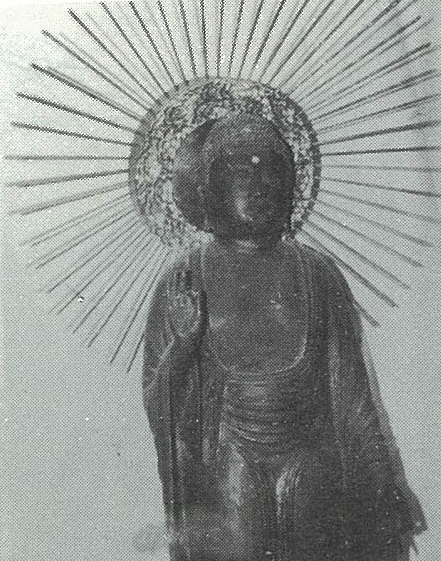建造物
この山門は、間口20.3m、奥行15.5m、高さ17mの総ケヤキづくりの建物である。
山門の建築は、天明5年(1785)に京都東本願寺棟梁柴田新八郎を棟梁に始められたが、天明8年(1788)、焼失した本願寺の再建が始まったため京都に引き返した。その後副棟梁松井角平恒徳(2代)が棟梁となり完成した。
細工の多くは井波大工の力作で、井波彫刻のもとになったものである。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和40年1月1日
建造物
八幡宮本殿の西南側に、城跡の土塁が連なり、その内側高台に飼蚕堂とも呼んでいる養蚕社がある。井波の蚕堂は、「こがいさま」とよんでいる蚕の霊を祀るために社殿がつくられたものである。
文久元年(1861)に創建された蚕堂の社殿は、井波の宮大工松井角平が建造した。小堂ではあるが、見事な木組みと細工が施され、随所に井波大工の技が見られる。
所在地:南砺市井波3057
所有・管理者:井波八幡宮
指定年月日:平成15年11月27日
建造物
太鼓堂は天保13年(1842)に再建されたものである。念仏、読経などをする時刻を告げるために、ここにある太鼓を鳴らしてきた。
瑞泉寺11代浪化が、この太鼓堂を司晨楼と名づけた。晨というのは、朝という意味で、早朝に時をつげるという意味がある。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和30年7月