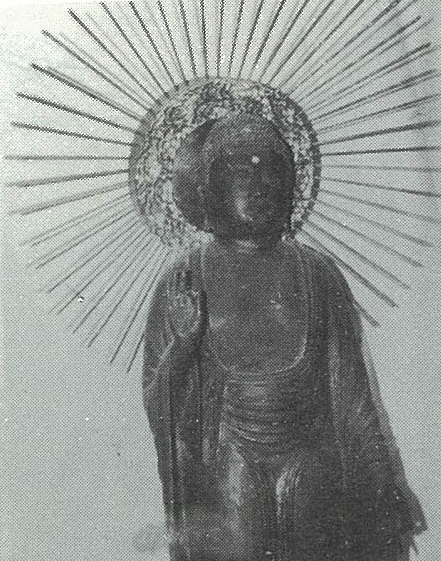史跡
この廟は、瑞泉寺を開いた綽如上人をはじめ、代々の瑞泉寺住職を祀った墓である。
瑞泉寺歴代の火葬場は井波町郊外五領(御陵)並びに庄川町ポンポン野にあった。
宝暦4年(1754)に瑞泉寺境内に墓をまとめて移し、安永4年(1775)、瑞泉寺再建と共に、ここ大谷の小山拝領地に移した。
同10年には井波墓地が形成され、墓守の堂舎を建てスギ・ヒノキなど2000本を植林して景観を整えた。
所在地:南砺市井波2630
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和30年7月
史跡
平安時代の記録である「延喜大学寮式」にそのころの国の役人を育てる大学の学生に与える食費を得るために、越中国砺波郡に大学寮を置いたことが書かれている。井波に勧学院の地名が残っていることから、このあたり一帯に勧学田があったと考えられている。
また、この付近には、奈良の東大寺の荘園があり、このあたりの水田が、東大寺勧学院の米を生産していた跡だとも言われている。このあたりは古くから開け、中央の朝廷からも重要な地域として扱われたいたことがわかる。
所在地:南砺市高瀬135
所有・管理者:南砺市
指定年月日:昭和41年7月1日
史跡
瑞泉寺は、明徳元年(1390)に本願寺五代綽如によって開かれた。綽如は浄土真宗の教えを北陸地方に広めるために、井波の地がふさわしいろ考え、後小松天皇の許しを得て、北陸の各地から寄付を集め、寺を建てた。
現在の本堂は、明治18年(1885)に再建されたもので、間口45.5m、奥行42.7mもあり、北陸地方の真宗木造建築の寺院としては、一番大きな建物である。棟梁は、井波彫刻の松井角平恒弘や井波大工、井波の彫刻師が工事の中心となって完成した。
所在地:南砺市井波3050
所有・管理者:瑞泉寺
指定年月日:昭和30年7月