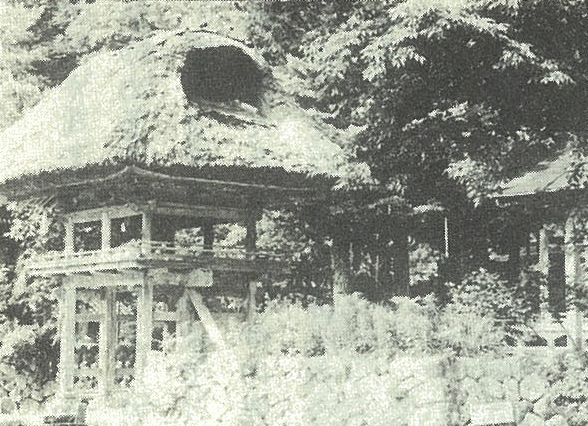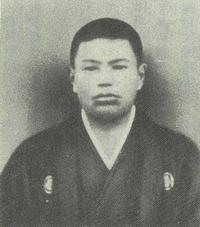偉人
岩瀬十次郎は、明治10年(1877)上平村西赤尾町、岩瀬十平の長男として生まれた。
岩瀬家は、代々「岩瀬」とよばれ、広い土地や、たくさんの山林をもつ村の有力者であった。そのうえ、十次郎は、幼い時から物おしのしない快活な少年であっ た。成長するにしたがって、さらに度量が大きく落ち着きのある風格を備えるようになった。身長は5尺7寸もある堂々たる体格であった。
<西赤尾の結約書>
十次郎が村のために最初に活躍したのは、明治26年(1893)、10才のときである。
そのころ五箇山は、わずかの傾斜地を利用して稗・粟・そばなどを作り、それらをまぜたご飯を毎日の食事としていた。村では、米がほとんどとれず、繭や生 糸・木炭・和紙などを城端へ運び、判方(商人)に売ってその代金で米を買っていた。米ばかりのご飯は、正月かお祭り、報恩講さまなどのときにしか食べるこ とが出来なかった。そのため、「白い飯が食べたい」「米をつくりたい」というのは、五箇山に住む人々のねがいであった。
十次郎は、この貧しい村のようすを見て「なんとかして、五箇山でも米作りができるようにしたい」と人一倍思っていた。そして、父とともに村のあちこちを見てまわり、水田の適地を探し求めた。
しかし、水田を開くには、まず水を引かねばならなかった。水源地を求め、さらにそれを引く用水路が必要なのである。ところが、西赤尾では土地についての利害がからみ、それぞれが自分勝手な意見を出して、なかなか用水路新設の工事にとりかかれるような状態ではなかった。
このような現状を見て十次郎は、個人の利害関係で争っていては、いつまでも開田できないことを切々と、しかも情熱をもって村民にうったえ、小異を捨てて大同につくべきであるということを論し、ついに村民の同意を得ることに成功した。時に十次郎16才であった。
「本村において、以降、用水を工事いたすことについては、拙者の所有地に向かい候とも 一同かれこれ補償申さず候につき、この段、協議の上、連署を似て後日のため 結約いたしおき候也」
これが有名な「西赤尾の結約書」で、西赤尾全戸の署名と捺印があり、村の一致団結を示すものとして、その後の改開田事業等に大きな示唆を与えたものといわれている。
<平草嶺で水田の試み>
明治31年(1898)十次郎は、草谷川の上流7キロメートルの平草嶺に3反歩(約30アール)の原野を開墾し、水田の開拓を始めた。平らに見える土地ではあったが、やはり山の傾斜地である。くわやつるはしで平坦な水田を造ることは、たいへんな苦労であった。
その年、ようやく開田にこぎつけた十次郎は、田植えを始めた。しかし、稲は伸びず、枯死してしまた。あまりにも上流であるため、雪どけ水が冷たく、稲の生育に適さなかったのである。
<岩島における開田>
この失敗を生かした十次郎は、つぎの開田の地として岩島に目をつけた。
そして取水口を、草谷川の支流脇谷にとった。脇谷の水を、山まわり約1キロメートルの用水路を掘り、岩島地内までに引いて水田をつくったのだ。そこで田植 えをしたところ、こんどは見事に成功した。明示33年(1900)のことで、今まで、沼田にしか作れなかったこの地区で、はじめて、本式な水田による稲作 が実現したのだ。
<独力で水路トンネルを>
しかし、喜びもつかの間、その年の冬、岩場にかけてあった木の樋が、積雪によってこわされ、水が通らなくなってしまった。
そのうえ、長い用水路のため水もれがひどく、予想していたよりもはるかに少ない水量になってしまった。さらに、水もれのために山くずれの心配があるという苦情もでるようになった。
そこで、十次郎は水路トンネルを掘ることを決めた。約200メートルの長さである。明治38年(1905)10月、県知事の許可をもらって、いよいよ工事 にとりかかった。しかし、今でもむずかしいトンネル工事を、専門の建設業者を頼むわけでもなく、しかも幼稚な道具や機械を使って掘ったので、なかなか工事 は進まなかった。
そのうちに大きな岩盤に出あった。夜も休みもなく3交替制で人夫を督励していたが、1年間でつくりあげるという期限がまたたく まに過ぎてしまった。十次郎は、さらに1年間の期限を伸ばしてもらうように願い出た。自費で工事をしているということで、特に許可された十次郎は、さらに 工事を続けた。いつも人夫の先頭にたって穴掘りに精を出した。せまくて低いトンネルの中で、ろうそくの火を竹筒でのぞいて方角を決めたり、高低を測るとい う簡単な方法であった。人夫たちは不安に思い、特に夜の作業は、みんなきらったが、十次郎は自分1人になってもこの仕事をつづけて、その完成にむかって全 力をつくした。
「この工事でトンネルがつぶれるか、岩瀬がつぶれるか」といわれたのは、このときのことである。
明治40年(1907)9月1日、3年間の年月と、ねばり強い十次郎の執念とによって、ついにトンネルは貫通した。
このトンネル工事は、山の両側より同時に堀り進められるものであり、中でうまく結ぶことができるかどうか、取入口と出口との高低が逆にならないかなど心配 は絶えなかったが、貫通したときは、30センチメートル出口から掘った方が低かったので大成功だった。十次郎はもちろん、関係した人たちの喜びは、どんな であったろう。貫通の日は夜を明かして祝ったということである。
偉人
<寛大な人がら>
十次郎は、このトンネルを掘るにあたって、岩島地内に土地をもつ下島部落の人にも加入を呼びかけた。しかし、トンネルが掘りぬける見通しもじゅうぶんないのに、多くの費用や労力がかかるので、だれも賛成する者はいなかった。
ところが、トンネルが貫通して岩島に米作りができるようになると、下島部落の人たちも水を使わせてほしいと願い出るようになった。十次郎は、以前のことに
はこだわらず、快くそれを許したので、下島の人たちは十次郎の寛大な人がらに感激したという。今でも岩島地内に見られる4町歩(4ヘクタール)の美由は、
それによるものである。
<村の教育行政に貢献>
十次郎は、明治37年(1904)、27才の若さで村会議員に選ばれ、後に郡会議員にも推された。さらに明治42年(1909)、上平村の村長に就任し、村政の発展と村民生活の向上に尽力した。
村長在任中の大きな仕事の1つに、学校の整備があげられる。そのころは、上平小学校の本校は細島にあり、楮・西赤尾・新屋・皆葎・猪谷の5地区に分教場があった。いずれも、校舎はせまく、そまつであり、学習用具もほとんどみるべきものがなかった。
村長になった十次郎は、教育の重要なことを村民に説き、分教場の存続を願う人々の心もくみながら、上平村に西赤尾小学校と皆葎小学校に2校を創立し、設備の充実に努めた。
なお、晩年に村の学務委員を務めた。昭和9年(1934)には、西赤尾小学校に高等科を設置することを計画し、自ら委員長となって学校の増築をなしとげ
た。この年、庄川が大洪水になって、校舎を建てる用材が多く流され、一時は増築工事も危ぶまれたが、十次郎は苦境を乗りきって落成にこぎつけた。高等科新
設という大きな事業のかげには、このような十次郎の苦労もあったのである。
<初代消防組頭>
大正4年(1915)、十次郎は上平村に初めて消防組を組織し、初代組頭の役についた。
そのころの消防は、今のような機械力による消防ではなく、火事になれば手桶で水をかけるだけの消火の仕方であった。焼死しないように逃げることと、身のまわりのわずかな着物を持ち出し、火の燃えつきるをただ見守るだけであった。
十次郎は、まず新しい型の腕力ポンプを買い入れた。設備をよくし、消防演習もときどき行って、消防組の組織を強め、消火技術を高めるよう努力した。このようにして、18年間も組頭として村民の生活安定のため尽くしたのであった。
昭和10年(1935)2月25日、少年時代より頑健だった十次郎も、むりがたたったのか病気にかかり、59才でこの世を去った。村人たちは深くその死をいたみ、慈父を失ったように悲しんだという。
昭和25年(1950)十次郎を尊敬し、讃える人たちの手によって、西赤尾八幡社の境内に石碑が建てられた。ちょうど西赤尾小学校(上平小学校)を見守るかのように。
偉人
〈人となり〉
中谷豊充は、明治18年(1885)中谷豊平の長男として上平村細島に生まれた。生まれつき頭がよく、しかも勉強好きな子で、両親始め一家の大きな期待を掛けられて成長した。
性格は大変優しかった。虫や動物などをじっと見つめていることもあった。やんちゃ盛りの少年になっても、あまり他の男の子のように悪戯することも少なかった。それでも、別に偉ぶっているわけでもなく、遊ぶときには夢中になって夜、暗くなって帰らないことも珍しくなかった
父豊平は漢方のお医者さんであった。その頃のことであるから専門的な医学を修めたわけではなく、五箇山に野生している木の皮や草の根や葉などを乾かして薬 を調合し、病人に与えていたのであろう。それで村人達が、絶え間なく家を訪れて教えを乞うた。その温かい人柄と幅広い知識は、土地の人達に大変尊敬され親 しまれていたのである。 このような雰囲気の中で育った豊充は、生まれつきの優しい性格と共に、「医者として是非世の中のために尽くそう」と、知らず知ら ずのうちに決意していったのであった。
〈松村謙三との出会い〉
豊 充は、細島の小学校から城端の高等小学校へと進んだ。そこを優秀な成績で終えると、明治32年県立高岡中学校へ入学した。その頃の高岡中学校というのは、 呉東にある富山中学校と共に県下でも最も優秀な人達の学ぶ学校であった。豊充は城端の町で下宿しながら五年間、高岡へ通ったのである。
その頃、福光町から松村謙三氏が、やはり高岡中学校へ通学していた。松村氏は豊充より2年先輩であったが、通学する方向も同じだったので、2人は仲良しになった。
豊充は何事も、このよき先輩に相談した。先輩もまた、この静かで勉強一途に励む後輩に目をかけた。授業が終わってから2人は、肩を並べて家路を辿った。時 には、高岡から福光まで20キロの間を歩き通して語り合ったこともあった。その頃の中学生にはそれだけ歩くことぐらい苦にならないことであったのだ。当時 は日清戦争に勝利を収め、日本の興隆期でもあった。やがて松村先輩は早稲田大学に進んだが、医師になって郷里五箇山に身を捧げようとしていた豊充は、その 2年後に金沢医学専門学校で医学を修めることになった。しかもこの時に育まれた友情と、人間に対する強い愛情や、社会に対する広い見方は、その後の豊充の 人となりに大きな影響を与えた。
〈五箇山で初めての開業医〉
大正5年かねてからの念願であった医師として、豊充は郷里五箇山へ帰ってきた。両親や家族はもとより、五箇山中の人々が喜んで迎えた。今まで無医村だったこの五箇山に、近代医学を身につけた若い医師がやってきて診察に当たるのである。しかも五箇山出身の人ではないか。
豊充は、五箇山の中心である下梨に民家を借りて改装し、「中谷医院」の表札を掲げた。今の国道156号線と304号線の分岐点のあたりである。その医院 は、玄関を入ると待合室、そして診察室兼薬局、それに居間という簡単なものであったが、豊充の五箇山住民に対する深い愛情と、人間の生命を預かる医師とし ての使命感にあふれる館となった。
それまでの村人達の医療は大変なものであった。お医者さんに懸かるときは、どうしても峠を越えて城端の町まで 出なければならず、まして、冬季は命懸けであった。それで当然手遅れとなり、助かる命を亡くした人も沢山いた。そこへ豊充が帰ってきたのである。五箇山の 人達の喜びと期待はどのようなものであったろう。
〈豊充の診察〉
豊充は期待に応えて、医師として精一杯に活動した。誰彼となく丁寧に診察を始めた。専門の内科はもちろんのこと、外科も診たし、神経科の病人さえ通った。 1人1人に的確に指示を与え、施薬した。病気が全快する人々が次々と現れると、益々評判がよくなり忙しくなった。どんな忙しいときでも常に微笑を忘れな かった。静かな声で話す一言、一言はその人の心を癒し、益々、村民の信望を高めていった。真っ白い診察着をまとい、白面で長身であった。人々は脈を診るた めに手を持つと、もうそれだけで病気が治ったような気になった。それくらい医師と村人との信頼関係が出来ていたのであろう。
下梨で開業した翌年、上平村の人達の懇望に答え、細島の自宅でも診療を始め、週1回はここへも通った。往診にも回ったそんな時には自転車に乗った。五箇山で初めての自転車である珍しい自転車に乗った先生が来られると、家の人達は玄関へ出迎えに出るほどだった。
豊充は、あまり金銭にはこだわらなかった。苦しい家計の程が分かるだけでなく、医は仁術であると言うことを身を以て知っていたからであろう。
〈雪の日の豊充〉
大正14年2月、下梨の中谷医院へ上平村の真木から、産気づいたようだから直ぐ来て欲しいという報せが届いた。外は猛烈な吹雪である。しかも積雪は2メー トルを超えていた。家人は、こんな悪天候の日にと言って往診に強く反対した。「よし、行く」と、出迎えの人の前できっぱりと答えて、直ぐ出発した。下梨か ら真木まで15キロメートル、しかも、途中は「雪崩の巣」である。人々は声を掛け合い、助け合いながら進んだ。本当に命懸けの往診であったが、夕方6時頃 に真木の家に着くことが出来た。豊充は疲れも見せずに診療を始め、無事に男の子が生まれた。「あの時の有難かったことは、今も忘れることが出来ない」と、 60年後の今でも、その人は感謝の気持ちを話してくれた。
〈学校医として30年〉
豊充は、大正5年に下梨小学校の「学校医」に委嘱された。東中江、皆葎、西赤尾の各小学校の「学校医」も兼ねることになり、平・上平村全部の青少年の保険・衛生に直接関係することになった。しかも、これは昭和20年に亡くなるまで実に30年も続くのである。
先ず、手がけたことは衛生観念の普及であった。衣服の洗濯、入浴、洗髪など身近な清潔を守る生活習慣を身につけるよう説いた。「衛生デーを設けて、常にこ れを奨励諭示し、受け持ち教諭はこれを調査し・・・・」と、下梨小学校の沿革史に載っている。 また、暖簾や掛け筵莚、裸足、手洗水、寝所の採光や換気、 万年床、炊事場、食器の洗浄、飲料水、食物、掃除、虫歯など、家庭の基本的な生活様式や日常生活の中味についても学校を通して指導したのである。
昭和15年夏、下梨を中心に腸チフスが発生し、運悪く蔓延した。この時は、消毒や予防に骨身惜しまず活動して、その被害を最小限に食い止めたのであった。
その後、社会の進歩もあり、生活も向上し、衛生思想も徹底してきた。体位も年々向上して現在に至っているが、その影に豊充らの血のにじむような努力があったのである。