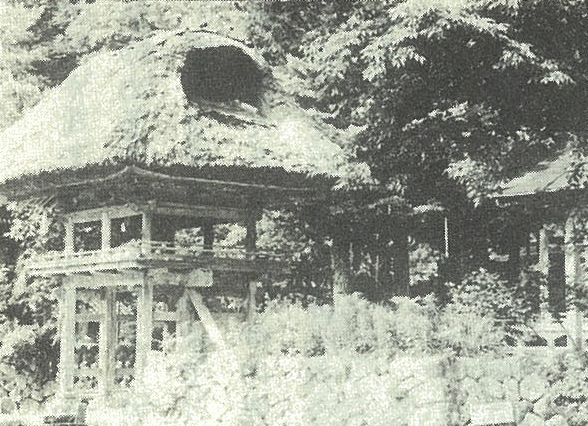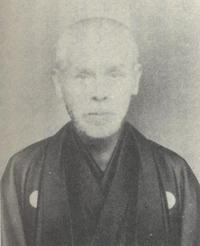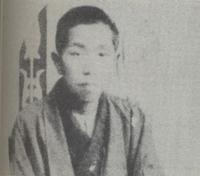偉人
〈村長として村に貢献〉
医師となって6年目の大正11年、思いがけず上平村の村長になることになった。父豊平も村長を務めた人であり、伯父の生田長四郎もまた、明治22年に上平
村の村長を15年務めた人だったから、豊充も政治に無縁ではなかった。然し医療に専念したいので再三に亘って村長就任を断った。それでも、村人達はどうし
てもそれを許さなかった。
丁度、大正の中頃は、上平村では南部と北部とで主導権争いがあった。それで、中間にあり、人格者でもある豊充が村長に
選ばれたのであるが、就任第1回の村会で速くも意見が衝突してしまった。この時、静かに聴いていた豊充は、すっくと立って、自分の所信をはっきりと説明し
た。そして、なんと四時間も演説をし続けてその場を旨く収めたという。それで村制の危機も収まり、平和なもとの村にかえり、豊充の内外における信望も更に
高くなった。
その他、豊充は医師として忙しい体であったにもかかわらず、村政の確立に多くの功績を残した。
村長に就任したその翌年、細島村耕地整理組合を組織して同地内に約四町歩の開田に成功した。これは上平村で、明治30〜40年代の西赤尾上野開田、下島開田につぐ本格的な開田で、その後の米の自給体制確立へ大きな布石となった。
〈村政百年の大計を〉
上平村の村政が飛躍的な発展を遂げたのは、やはり電源開発であった。
昭和5年に庄川下流の小牧、祖山に発電所が建設され、電源開発は徐々に上流に向けて進められていた。昭和電力は、次のダム建設予定地を上梨下流から現在の
小原地点へと変更し、昭和10年に測量・ボーリングに着手した。豊充は村政百年の大計を考え、村有志と共に「発電事業誘致委員会」を結成し、積極的な協力
体制をとった。祖先の墳墓の地に対する愛着や用地の買収、水没地の補償など、村民感情や利害相反する人達の間で双方の中に立ち、誠意を持って問題の解決に
努力した。
昭和14年8月、上平村や富山県の要望に応えた昭和電力は、小原ダム工事に着手した。同年12月、工事は日本発送電の引き継がれた
が、昭和17年冬、遂に小原ダムは湛水を始め、3万5千キロワットの小原発電所が発電を始めた。この工事によって、発電もさることながら、村内には17町
歩の開田がなされた。道路もよくなり、経済的にも文化的にも、村政や村民の生活向上に与えた影響は、計り知れないものがある。
その後、成出、新成出、赤尾、新小原等上平村内に大きな発電所が相次いで出来、更に境川の総合開発へと繋がっていくのである。
〈細島橋落下事件〉
豊充が村長に就任したその年11月10日、上平村に大事件が起きた。それは、演習中の金沢第9師団の兵隊が行軍中、細島吊り橋を渡り終えないうちに、橋の支柱が倒れて大きな音とともに庄川へ落ち、沢山の犠牲者を出した事件である。
その日は、あられ混じりの雨が激しく降り、凍えそうな寒い日であったという。事件が起きたのは午後8時頃であったが、急を聴いて駆けつけた豊充は、先ず負
傷した兵士の応急の処置を執った。数人の死者や、数10人に上る重傷者の中で、現場は大変な混乱であった。それでも豊充は落ち着いて人命の救助に最善を尽
くしたのであった。
豊充の医師としての誠意ある態度や、村長としての冷静な判断は、多くの人々に深い感銘を与え、事件が収まってから第9師団の師団長から懇ろなお礼の手紙が届いたということである。
〈初代の郵便局長として〉
下梨に郵便局が設けられたのは明治15年のことである。
昭和2年城端町と郡上八幡とを結ぶ八幡道路が出来た。これを機会に、兼ねてから要望していた上平郵便取扱所を自宅に設けた。葉書や手紙、小包等の郵便物、
為替、貯金、簡易保険、郵便年金などを取り扱い、鳥も通わぬ五箇山と言われた最奥の地にも、文明の光がもたらされるようになった。昭和12年郵便局に昇
格、16年には電信電話事業を開始したが、豊充は亡くなるまで局長として地域の人々の生活向上に寄与した。
〈顕彰のこと〉
昭和20年5月25日、豊充は静かに60才の生涯を閉じた。
村長として、水田開発の恩人として、電源開発の先駆者として、上平郵便局の創設者として、数々の足跡を残されたが、五箇山最初の医師として、その全生涯を僻地医療に捧げられたご功績は誠に大きいものがある。
温和な人柄と毅然たる態度は、文字通り五箇山の人々の賛仰の的であったといっても過言ではない。
今、細島に、松村謙三氏の揮毫になる顕彰碑があり、そのかたわらに、「五箇山広シト雖モ、直接間接恩顧ニ触レサル人ナク」と刻んでその生涯を讃えているが、宜なるかなというべきであろう。
偉人
山崎宗繁は、明治6年(1873)平村上梨に生まれた。
村の中心人物として活躍し、平村村長をはじめ、数々の役職を歴任して五箇山の発展に尽くしたが、蚕種をはじめ養蚕・製糸業、さらに製薬業から酒造業に至るまで、地元の産業育成に心血を注いだ事業家であった。
〈生いたち〉
山崎家は、代々「宗七」を名乗り、藩政時代から村肝煎りを続けた上梨きっての素封家であった。父宗七も農業のかたわら、繭の仲買商人として手広く商売を し、その商圏は五箇山のみならず、遠く岐阜県の白川村までにも及んでいた。そのうえ、金融業・酒造業を営み、生活が裕福であった。
宗繁は明治14年満6才になると城端小学校に入学した。小学校時代を城端町で過ごして、新しい友人達と交際する機会を得た。これがその後の事業や信条に大きな影響を与えたと言えよう。
14歳の時、父が亡くなると、直ちに帰郷して家業を継ぎ、家代代の上梨村総代を務め、一躍して村の中心人物となった。
〈新しい知識を求めた勉強家〉
宗繁は、非常に向学心の強い人で、よく読書をし、自分の部屋に座ったきりで、常に机に向かっていたという。中でも歴史書を愛し、「日本外史」や「十八史略」などは、気に入ったところは暗記してしまうまでに読み続けた。
明治35年29歳の時わざわざ東京に出て、神田で行われた普通文官の講習会にも参加して熱心に勉強を進めた。普通文官講習会とは役人を養成する講習会で、そのころの宗繁の学問に対する心意気が分かってほほえましい。
宗繁はまた、英語の知識の必要性を強く感じていた。明治の中頃のことでもあり、五箇山は勿論、富山県でもそんな進んだ考えを持っている人が極めて少なかっ た中で、そのような見識を持っていたとは驚くべき事である。直接教えてくれる人もなく、もっぱら通信教育などを利用して独学で始めたものである。しかも、 死ぬまで英語の辞書を座右に置き、それをひもとく努力を忘れなかった。
また、常に、国内の動向や世界の情勢を知るために、その頃未だ読む人が少 なかった「新聞」を送ってもらい、広告も含めて隅から隅まで丹念に読んで、自らを啓発していたという。その頃の五箇山への新聞は、数日遅れで届いたもので あったが、宗繁はそれによって確実に世の中の情勢を掴み、新しいニュースをいろいろと村人に伝えたのであった。
現在、山崎家には、宗繁が自ら書いた式辞・祝辞の原稿、あるいは演説を書き写したノート、そのほか「諸事覚え書帳」などが数多く残されており、一生、勉強をし続けた宗繁の面影を見ることが出来るのである。
〈常に積極的に新しい事業を手がけた人〉
宗繁は、家業の酒造業を続けるかたわら、この山村に適するさまざまな産業の開発に努めた。もともと五箇山には医者が居なかったので、それをみかねた宗繁 は、自分で医学の本を取り寄せて勉強し、明治25年に「製薬営業」の免許を取った。そして、金沢や平野部の町々から買ってきた薬を、病状に合わせて調合し 病人に与えた。また広く村内に自生するゲンノショウコ・ドクダミ・キハダなどの薬草を調べて採取し、薬用に使用したこともあった。
今の医師と薬局を兼ねたようなことをしていたが、貧しい人からは、一切代金を貰わず、無料で分けた。命を救われた人を始め村人達は、有難く思って山で穫れたキジや珍しい御馳走などを持ってきて、お礼の気持ちを表したということである。
しかし、細島の中谷氏が五箇山で最初の医院を開業した時を境に、薬を調合することを辞めた。よく勉強した人だけに自分の施薬についてもその限界をよく知っていたのであろう。
養蚕・蚕種・製糸業は、明治時代を通じて、五箇山の最も重要な産業であった。宗繁もまた、この振興に心を砕いた。明治40年大日本蚕糸会富山支会議員など 業界の役職に就いた。自らも製糸工場を経営したり、蚕種業を開業したこともあった。昭和4年世界恐慌のおりには、生糸の価格が暴落し、宗繁自身はもちろん のこと、五箇山全体が大打撃を受けたことがあった。地域の産業振興を目指す宗繁にとっては、非常に苦しい時期であった。
また大正の頃、宗繁は山地に適する産業として漆の栽培に将来性を見いだした。地質や適正をよく研究した上で、沢山の苗木を購入して栽培を試みた。然しその後、中国産の安い漆が輸入されるようになり、価格が著しく暴落しため大損害を受け、この事業は挫折してしまった。
〈五箇山の味覚、銘酒三笑楽〉
宗繁の興した事業の内で、結果的には成功しなかったものも多かったが、酒造業は今も続けられている。父の宗七時代から受け継いだものであったが、宗繁の時 代に品質の改善、販路の拡大に成功し、「五箇山の人々の口に合う美味しい酒」としてもてはやされるようになった。時には醸造した酒がみんな腐って全く売れ なく、経営的には大変苦しいこともあったが、新しい杜氏を招き、製法を研究した結果、厳しい自然の中で生活する五箇山の人々に最も喜ばれる味覚の酒が常に 製造できるようになった。これが今日、銘酒「三笑楽」として広く人々に親しまれているのである。この酒造りは宗繁の旺盛な事業家としての活動を支え、昭和 の初期では、五箇山全体でも経済力は抜群であったと伝えられている。
〈村役としての活躍〉
また宗繁は、数々の事業を積極的に進める一方、推されていろいろの要職にもついて郷土の発展に尽くした。明治40年からは郡会議院8年、大正5年から平村村長2期、その他、郡や県の実業界の役職などを殆ど勤め上げた。
区長をしていたとき、年貢の受け取りを全部引き受けたり、子供の名付け親になったり、心配事の相談に乗ったりして、山崎家には訪問客が絶えなかった。ま た、県や郡から来た役人の巡視に際しては、五箇山の生活の厳しい実情をつぶさに説明し、自宅を宿舎に提供するほどの熱心さであった。
〈村人に慕われ、尊敬された人柄〉
宗繁は、豊かな資産と持ち前の積極性を十分に発揮して、新しい事業に取り組んだ人であった。時には事業に難航し、家財を市に出して売ったり、先祖伝来の土 地や、杉の美林を手放したりしたこともあったが、強い精神力とこだわらない性格でこれを克服して五箇山の発展に尽くした。
私欲が無く、また非常 に思いやりのある人でもあった。近くに貧しい人があれば食物や衣類などを惜しもげなく分け与えた。自立できない人は奉公人として自宅に住み込ませたり、人 夫を雇った時には、その日のうちに賃金を支払ったということもあった。これらのことから、村人達の尊敬を一身に集めていたのである。
昭和17年5月6日明治・大正・昭和の3代に亘り、五箇山の政治・経済に大きな業績と、おおらかな人柄による多くの逸話を残して、宗繁は波乱に富んだ一生を静かに終えた。69才であった。
1代の事業家であった宗繁が手がけた事業にうち、現在に受け継がれているものは家業の酒造業のみとなってしまった。然し、明治以後の五箇山の経済的・政治 的発展と地域の人達の生活向上に尽くしたその業績は、郷土の先覚者として何時何時までも語り継がれていくことであろう。
偉人
〈生い立ち〉
藤井伝蔵は,文久3年(1863)11月9日、平村高草嶺藤井庄平の2男として生まれた。それは明治維新に先立つこと五年、世の中の移り変わりのめまぐる しいときであった。藤井家は、村でも指折りの資産家で、広い山持ちとして知られ、また、塩硝も造っていた。養蚕や和紙作りにも精を出し、製糸業をも手がけ て居たので家計は豊かであった。農繁期や蚕の盛んな頃になると、沢山の人を雇い、最盛期には70人分の食事を準備したと伝えられている。
少年時代の伝蔵は、一度聴いたことは絶対に忘れないと云うほど、優れた記憶力を持っていた。その上体も強く、風邪一つ引かずに育ってきた。遊びも村の中だけでなく、下梨やその他の村々までもよく出かけた。
〈学問への道〉
時代は明治となった。
「士農工商」の制度がなくなった。廃藩置県、学制発布、徴兵令布告、地租改正、新しい法律が次々と出て実行に移された。世の中の仕組みがどんどん変わり、人々の考え方や暮らしもそれにつれて大きく変わり始めようとしていた。
伝蔵には旺盛な知識欲があった。そしてよく読書をした。中でも歴史書を好んで読み、「日本外史」「三国志」などに没頭していた。電灯のない暗いランプの下 で、一心不乱に本を読む姿がよく見られた。動物や植物についても興味を持ち、道ばたの雑草の名前もよく覚えて知っていたし、昆虫の生態などにも詳しかっ た。
小学校を終えると、城端の町や福光の町の有名な師匠を訪ねて教えを乞うたが、それでも旺盛な向学心を十分に満足させることはできなかった。
明 治15年(1882)、遂に意を決して「学問の府」と言われた金沢の町へ出て学問の道にいそしむことになった。先ず門を叩いたのは有名な藤田私塾であっ た。そこで、四書(大学・中庸・論語・孟子)、五経(易教・詩経・書経・春秋・礼記)を中心に漢学を修めた。ついで、その翌年には関口塾に入門して算数・ 代数・幾何などを一年間学び、帰郷したのである。
〈教育者を志して〉
2年間に亘る金沢の遊学を終えて帰ってきた伝蔵の目に映った「郷土五箇山」の現実は、あまりにも低いものであった。その日の暮らしに追われ生活にゆとりがなかった。自分の名前さえも正しく書けない人がまだまだ多かった。
伝蔵が金沢で見聞した日本の新しい文明開化は、五箇山にはまだ程遠いものであった。時代の進歩につれて、五箇山の産業や暮らし、ものの考え方を高めていくためには、若い年代の人々に是非学問が必要であると、痛切に感じないわけにはいかなかった。
これからの世の中に生きて行くには、先ず子供達に読み書き、そろばんを初め一通りの教養を、必ず身につけていなければならないと考えたのである。
明 治17年(1884)伝蔵は、富山県師範学校へ入学の手続きを取った。これは五箇山で始めてのことである。伝蔵21才の春であった。こうして教育者として の道を歩み始めた。丁度この年、父藤井庄平は下梨村外37ヶ村の戸長に選ばれて行政の立場から村の発展に尽くすことになっていた。
明治19年必要な教養と学問を修めた伝蔵は、師範学校を終えて故郷へ帰り、まず、下梨小学校で、かねてから願っていた教育者としての第一歩を踏み出したのであった。
〈教育の道に精進〉
それから10年間、伝蔵は五箇山の子供達の教育のために日夜を分かたず精進した。明治20年から下梨小学校長、ついで、明治23年からは東中江小学校長を兼ねた。25年には、再び下梨小学校長となった。
その頃の学校は、今のように整った校舎や設備があるわけでなく、粗末なものであった。伝蔵は未来に望みを掛けて、精一杯子供達の教育に当たった。
明治6年に学校の制度が発足したものの、国民の生活が苦しかったので、子供達の就学率は極めて低かった。学校へ出るものは、昔からの家柄の子供とか特別な子供だけであり、「百姓の子供に学問は入らない」というのがその頃の普通の考え方でした。
子 供達も家の農作業の手伝いをした。蚕の桑こき、蚕の飼育、それに糸引きをした。男の子は少し大きくなると大人と共に山仕事に出かけた。女の子は「子守」を してよく働いた。その頃の学校日誌に「地方の不景気に伴い、保護者の資力大いに困窮し、生計の度も低く、子女をして家の手伝いを・・」と書いてあるが、当 時の様子をよく表している。学校へ出るのはせいぜい2割程度であったが、それも殆ど男ばかりで、女の子は1人居るか居ないかという状態であった。
教 師としての伝蔵は、1軒1軒足を運び、学問の必要性を説明し、学校への出席を促して回った。家だけでなく山の仕事場へ直接訪ねて、親に説いたこともあっ た。雨に叩かれて山道が崩れ難儀したり、夜が更けて暗い夜道を帰ったこともあった。わらじがけで橋のない庄川を渡り、危険な目にあったことも何度かあっ た。それでも伝蔵くじけなかった教育への熱意は、揺るぎないものであった。
更に部落毎に「教育談話会」を開いて、村の人々に語りかけた。昼間の激しい山仕事に疲れ切った人達であったが、尊敬している伝蔵の熱意に動かされ次第にその真意を理解するようになり、沢山の人が出席するようになった。
そのころの日本は、日清戦争という国の興廃をかけた大事件もあって外国と肩を並べるまでに列強の仲間入りをしょうという時でもあり、教育の重要性も一段と 高まった。このこともあって伝蔵の努力は次第に報いられた。明治39年(1896)の就学率は八割近くにまで達したのである。
〈郷土のために〉
伝蔵はまた、村の政治や産業の発展に積極的に新しい意見を出した。例えば、村が真剣に取り組んでいた北海道移民について意見書を出したり、下梨から下流の 金屋(庄川町)まで舟を通すため、庄川運漕株式会社を設立することにも努力し、また、山の神峠近くの猫池に鯉の稚魚を放流して飼育することを手がけたこと もあった。よいと思ったことには積極的に意見を出したり、自分で試みたりして村の新しい産業を探し続けたのである。
〈新しい天地を求めて〉
明治29年(1896)春、一切の公職から身を引き師範学校を終えて村に帰って丁度10年経っていた。その間に就学率の上昇もめざましく、学校制度も着々と整備されてきた。今の下梨小学校、東中江小学校の基礎を固めたのである。
伝蔵は、これを機会に大阪へ出ることを決意した。一家をあげて大阪へ移住した伝蔵は米屋を始めた。持ち前の研究熱心と努力で信用を得て商売は繁盛した。
明治33年伝蔵は風邪がもとで36才を一期としてこの世を去ってしまった。遺族は、伝蔵が生前あれほど慕っていた五箇山へ帰り、高草嶺の墓地に手厚く葬った。
高い理想を掲げ村の教育の基礎を作り、村の教育に全てを打ち込んだ伝蔵の魂は、今も私達の学校を見守り続けて居るであろう