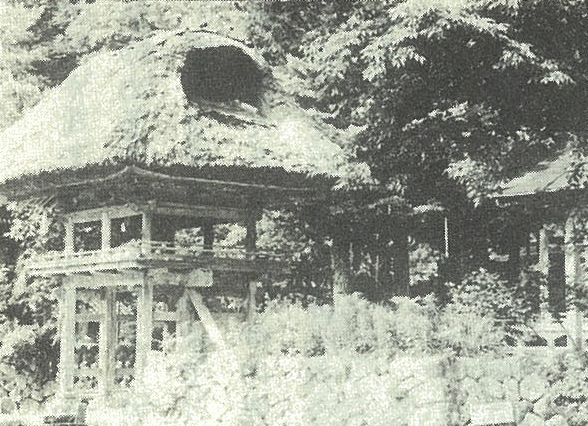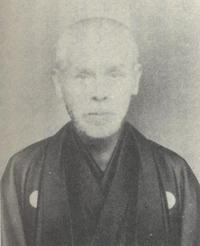山崎宗繁
偉人
山崎宗繁は、明治6年(1873)平村上梨に生まれた。
村の中心人物として活躍し、平村村長をはじめ、数々の役職を歴任して五箇山の発展に尽くしたが、蚕種をはじめ養蚕・製糸業、さらに製薬業から酒造業に至るまで、地元の産業育成に心血を注いだ事業家であった。
〈生いたち〉
山崎家は、代々「宗七」を名乗り、藩政時代から村肝煎りを続けた上梨きっての素封家であった。父宗七も農業のかたわら、繭の仲買商人として手広く商売を し、その商圏は五箇山のみならず、遠く岐阜県の白川村までにも及んでいた。そのうえ、金融業・酒造業を営み、生活が裕福であった。
宗繁は明治14年満6才になると城端小学校に入学した。小学校時代を城端町で過ごして、新しい友人達と交際する機会を得た。これがその後の事業や信条に大きな影響を与えたと言えよう。
14歳の時、父が亡くなると、直ちに帰郷して家業を継ぎ、家代代の上梨村総代を務め、一躍して村の中心人物となった。
〈新しい知識を求めた勉強家〉
宗繁は、非常に向学心の強い人で、よく読書をし、自分の部屋に座ったきりで、常に机に向かっていたという。中でも歴史書を愛し、「日本外史」や「十八史略」などは、気に入ったところは暗記してしまうまでに読み続けた。
明治35年29歳の時わざわざ東京に出て、神田で行われた普通文官の講習会にも参加して熱心に勉強を進めた。普通文官講習会とは役人を養成する講習会で、そのころの宗繁の学問に対する心意気が分かってほほえましい。
宗繁はまた、英語の知識の必要性を強く感じていた。明治の中頃のことでもあり、五箇山は勿論、富山県でもそんな進んだ考えを持っている人が極めて少なかっ た中で、そのような見識を持っていたとは驚くべき事である。直接教えてくれる人もなく、もっぱら通信教育などを利用して独学で始めたものである。しかも、 死ぬまで英語の辞書を座右に置き、それをひもとく努力を忘れなかった。
また、常に、国内の動向や世界の情勢を知るために、その頃未だ読む人が少 なかった「新聞」を送ってもらい、広告も含めて隅から隅まで丹念に読んで、自らを啓発していたという。その頃の五箇山への新聞は、数日遅れで届いたもので あったが、宗繁はそれによって確実に世の中の情勢を掴み、新しいニュースをいろいろと村人に伝えたのであった。
現在、山崎家には、宗繁が自ら書いた式辞・祝辞の原稿、あるいは演説を書き写したノート、そのほか「諸事覚え書帳」などが数多く残されており、一生、勉強をし続けた宗繁の面影を見ることが出来るのである。
〈常に積極的に新しい事業を手がけた人〉
宗繁は、家業の酒造業を続けるかたわら、この山村に適するさまざまな産業の開発に努めた。もともと五箇山には医者が居なかったので、それをみかねた宗繁 は、自分で医学の本を取り寄せて勉強し、明治25年に「製薬営業」の免許を取った。そして、金沢や平野部の町々から買ってきた薬を、病状に合わせて調合し 病人に与えた。また広く村内に自生するゲンノショウコ・ドクダミ・キハダなどの薬草を調べて採取し、薬用に使用したこともあった。
今の医師と薬局を兼ねたようなことをしていたが、貧しい人からは、一切代金を貰わず、無料で分けた。命を救われた人を始め村人達は、有難く思って山で穫れたキジや珍しい御馳走などを持ってきて、お礼の気持ちを表したということである。
しかし、細島の中谷氏が五箇山で最初の医院を開業した時を境に、薬を調合することを辞めた。よく勉強した人だけに自分の施薬についてもその限界をよく知っていたのであろう。
養蚕・蚕種・製糸業は、明治時代を通じて、五箇山の最も重要な産業であった。宗繁もまた、この振興に心を砕いた。明治40年大日本蚕糸会富山支会議員など 業界の役職に就いた。自らも製糸工場を経営したり、蚕種業を開業したこともあった。昭和4年世界恐慌のおりには、生糸の価格が暴落し、宗繁自身はもちろん のこと、五箇山全体が大打撃を受けたことがあった。地域の産業振興を目指す宗繁にとっては、非常に苦しい時期であった。
また大正の頃、宗繁は山地に適する産業として漆の栽培に将来性を見いだした。地質や適正をよく研究した上で、沢山の苗木を購入して栽培を試みた。然しその後、中国産の安い漆が輸入されるようになり、価格が著しく暴落しため大損害を受け、この事業は挫折してしまった。
〈五箇山の味覚、銘酒三笑楽〉
宗繁の興した事業の内で、結果的には成功しなかったものも多かったが、酒造業は今も続けられている。父の宗七時代から受け継いだものであったが、宗繁の時 代に品質の改善、販路の拡大に成功し、「五箇山の人々の口に合う美味しい酒」としてもてはやされるようになった。時には醸造した酒がみんな腐って全く売れ なく、経営的には大変苦しいこともあったが、新しい杜氏を招き、製法を研究した結果、厳しい自然の中で生活する五箇山の人々に最も喜ばれる味覚の酒が常に 製造できるようになった。これが今日、銘酒「三笑楽」として広く人々に親しまれているのである。この酒造りは宗繁の旺盛な事業家としての活動を支え、昭和 の初期では、五箇山全体でも経済力は抜群であったと伝えられている。
〈村役としての活躍〉
また宗繁は、数々の事業を積極的に進める一方、推されていろいろの要職にもついて郷土の発展に尽くした。明治40年からは郡会議院8年、大正5年から平村村長2期、その他、郡や県の実業界の役職などを殆ど勤め上げた。
区長をしていたとき、年貢の受け取りを全部引き受けたり、子供の名付け親になったり、心配事の相談に乗ったりして、山崎家には訪問客が絶えなかった。ま た、県や郡から来た役人の巡視に際しては、五箇山の生活の厳しい実情をつぶさに説明し、自宅を宿舎に提供するほどの熱心さであった。
〈村人に慕われ、尊敬された人柄〉
宗繁は、豊かな資産と持ち前の積極性を十分に発揮して、新しい事業に取り組んだ人であった。時には事業に難航し、家財を市に出して売ったり、先祖伝来の土 地や、杉の美林を手放したりしたこともあったが、強い精神力とこだわらない性格でこれを克服して五箇山の発展に尽くした。
私欲が無く、また非常 に思いやりのある人でもあった。近くに貧しい人があれば食物や衣類などを惜しもげなく分け与えた。自立できない人は奉公人として自宅に住み込ませたり、人 夫を雇った時には、その日のうちに賃金を支払ったということもあった。これらのことから、村人達の尊敬を一身に集めていたのである。
昭和17年5月6日明治・大正・昭和の3代に亘り、五箇山の政治・経済に大きな業績と、おおらかな人柄による多くの逸話を残して、宗繁は波乱に富んだ一生を静かに終えた。69才であった。
1代の事業家であった宗繁が手がけた事業にうち、現在に受け継がれているものは家業の酒造業のみとなってしまった。然し、明治以後の五箇山の経済的・政治 的発展と地域の人達の生活向上に尽くしたその業績は、郷土の先覚者として何時何時までも語り継がれていくことであろう。