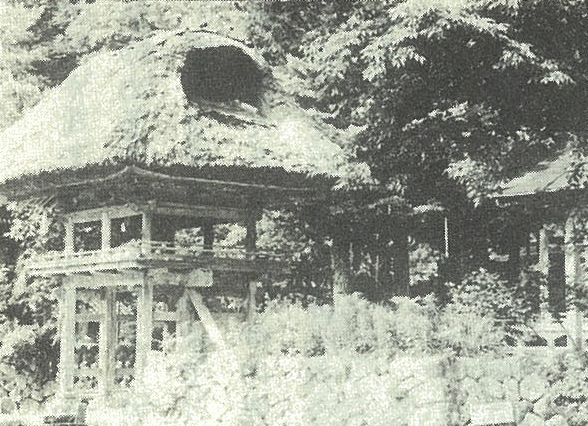偉人
<寛大な人がら>
十次郎は、このトンネルを掘るにあたって、岩島地内に土地をもつ下島部落の人にも加入を呼びかけた。しかし、トンネルが掘りぬける見通しもじゅうぶんないのに、多くの費用や労力がかかるので、だれも賛成する者はいなかった。
ところが、トンネルが貫通して岩島に米作りができるようになると、下島部落の人たちも水を使わせてほしいと願い出るようになった。十次郎は、以前のことに
はこだわらず、快くそれを許したので、下島の人たちは十次郎の寛大な人がらに感激したという。今でも岩島地内に見られる4町歩(4ヘクタール)の美由は、
それによるものである。
<村の教育行政に貢献>
十次郎は、明治37年(1904)、27才の若さで村会議員に選ばれ、後に郡会議員にも推された。さらに明治42年(1909)、上平村の村長に就任し、村政の発展と村民生活の向上に尽力した。
村長在任中の大きな仕事の1つに、学校の整備があげられる。そのころは、上平小学校の本校は細島にあり、楮・西赤尾・新屋・皆葎・猪谷の5地区に分教場があった。いずれも、校舎はせまく、そまつであり、学習用具もほとんどみるべきものがなかった。
村長になった十次郎は、教育の重要なことを村民に説き、分教場の存続を願う人々の心もくみながら、上平村に西赤尾小学校と皆葎小学校に2校を創立し、設備の充実に努めた。
なお、晩年に村の学務委員を務めた。昭和9年(1934)には、西赤尾小学校に高等科を設置することを計画し、自ら委員長となって学校の増築をなしとげ
た。この年、庄川が大洪水になって、校舎を建てる用材が多く流され、一時は増築工事も危ぶまれたが、十次郎は苦境を乗りきって落成にこぎつけた。高等科新
設という大きな事業のかげには、このような十次郎の苦労もあったのである。
<初代消防組頭>
大正4年(1915)、十次郎は上平村に初めて消防組を組織し、初代組頭の役についた。
そのころの消防は、今のような機械力による消防ではなく、火事になれば手桶で水をかけるだけの消火の仕方であった。焼死しないように逃げることと、身のまわりのわずかな着物を持ち出し、火の燃えつきるをただ見守るだけであった。
十次郎は、まず新しい型の腕力ポンプを買い入れた。設備をよくし、消防演習もときどき行って、消防組の組織を強め、消火技術を高めるよう努力した。このようにして、18年間も組頭として村民の生活安定のため尽くしたのであった。
昭和10年(1935)2月25日、少年時代より頑健だった十次郎も、むりがたたったのか病気にかかり、59才でこの世を去った。村人たちは深くその死をいたみ、慈父を失ったように悲しんだという。
昭和25年(1950)十次郎を尊敬し、讃える人たちの手によって、西赤尾八幡社の境内に石碑が建てられた。ちょうど西赤尾小学校(上平小学校)を見守るかのように。