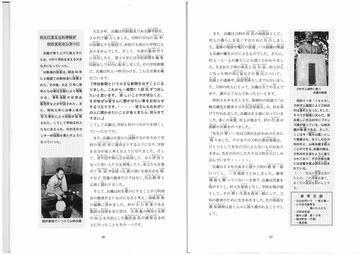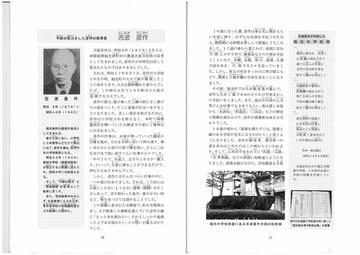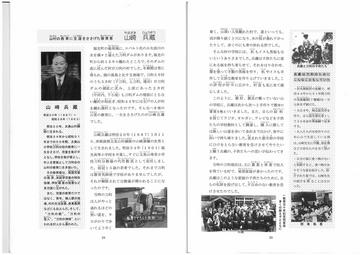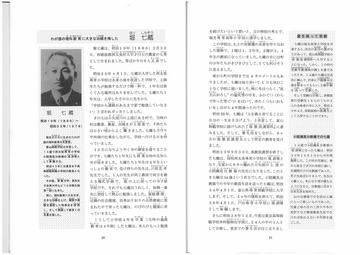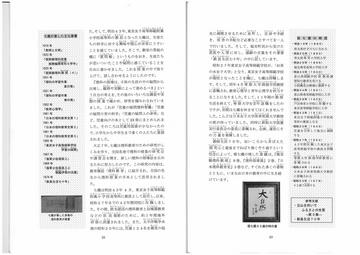明治9年(1876)〜昭和40年(1965)
福光新町の農家の長男として生まれる。
家が火災にあい、小学校に3年間学んだだけで奉公に出て苦労を重ね、苦学の末小学校教員となる。明治42年(1909)砺波中学校(現砺波高校)が設立す
ると教諭に迎えられ、昭和8年には校長となる。そして、”不断の努力”と”質実剛健”を信条として教育に尽くす。また、学校教育のみならず、社会教育にも
力を注ぎ、青年学校や幼稚園経営などの指導にも務めた。
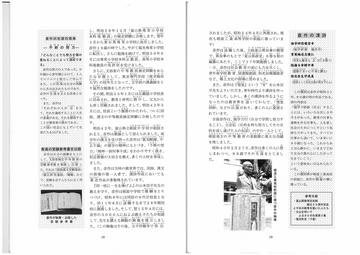
明治20年(1887)〜昭和38年(1963)
明治20年、太美山村綱掛に生まれる。明治34年から昭和31年までの55年間、太美山小学校刀利分校の教育に一生をささげ、児童を我が子となし、学校を
我が家とし、村人を家族として刀利谷の山村教育に生き抜いた。その教育愛は、貧困児童の救済、未就学児童の特別指導、学校環境の改善など多方面に注がれ
た。また、児童の教育だけではなく、青年、婦人層の指導、村の生活改善、産業振興などにもおよんだ。そして、”刀利の親”、”刀利の聖人”、”刀利の神
様”といわれ全村人から慕われた。