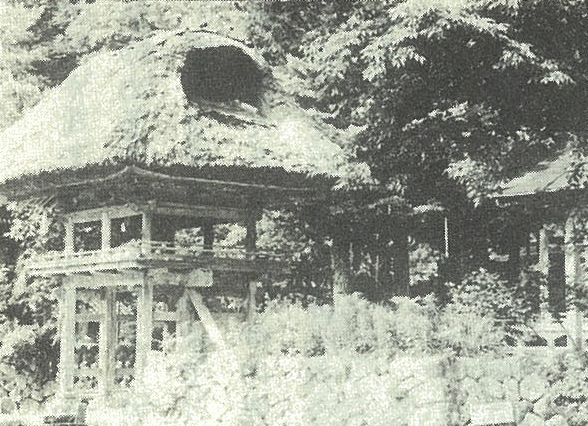水上善治
偉人
五箇山の産業の振興と交通路の開拓に尽くした水上善治は、文政11年(1826),南砺市高草嶺の藤井庄兵衛の2男として生まれた。安政3年 (1856)、28才の時、下梨の水上善三郎家を継ぎ、善三郎を名乗った。(その後善治と改名)明治31年(1898)この世を去るまで、五箇山の産業の 発展や、交通路の開拓、文化や教育のために活躍した地域の恩人である。
自分が決めたことは綿密な計画を立てて途中でどんな苦しいことがあってもくじけず、最後までやり通す強い精神力を持った人であった。
〈養蚕を五箇山の生業に〉
善治は弘化3年3月養蚕業の進んでいる信濃(長野県)、武蔵(東京都、埼玉県)、上野(群馬県)、下野(栃木県)、さらに東北地方の羽前〈山形県〉、羽後 (秋田県)、陸奥(青森県)などの各地を歴訪した。嘉永3年(1850)には、上野国群馬郡烏村の田島弥平について養蚕飼育法を学び、そこで製造した新し い蚕種を買い求めて帰り、五箇山の人に無料で配って蚕の育て方を教えたが、その結果は、とても良い成績であった。時に22才。これに自信を得た善治は、そ の後続けて、桑・蚕種・養蚕・製糸など養蚕業の振興に全力を尽くす。このように再三にわたる各地への歴訪は、全て徒歩によるものであった。険しい山道を歩 き、橋のない川を渡るということは大変なことで、時には野宿をしなければならぬ事もあった。
世の中が改まって、明治になると、五箇山の経済も大きく変わってきた加賀藩がなくなり、塩硝の生産が中止され、善治ら村の指導的地位にある人々の苦悩は大変なものであった。そこで、塩硝にかわるものとして養蚕業や和紙の製造に活路を見いだそうと苦心したのであった。
明治13年蚕の新しい飼育法を広めるため、講師を招いて、「養蚕伝習所」を下梨小学校内に開設し、五箇山の各地より、20名を選んで、温暖飼育法を学ばせ た。その翌年には下梨・皆葎・東赤尾・下出・高草嶺の各地に「養蚕伝習所」を設け、それぞれ20名ずつ、生徒を募集して実習させたので、五箇山に新しい養 蚕飼育の方法が普及した。また、この費用は殆ど善治が私財を寄付して出来たものであった。このように善治は、新しい時代にふさわしい養蚕飼育法の改良普及 に尽力した。
さらに、「よい繭糸はよい桑から」を信条に、桑園の開拓にも努力した。土地が肥え、日当たりのよい場所を選んで桑の苗を植えさせ た。苗木は、本場の信濃(長野県)から取り寄せたりして、全国からよい苗木を選び、桑の葉のよくとれる品種をみつけて五箇山の各地に植え付けをしたのであ る。
また、製糸の方法についても優れた考えをもっていた。明治11年(1878)、善治は、小谷川の水力を利用して製糸工場を造った。これは、 五箇山で、動力を利用した工場の第1号である。それまでの製糸は、手繰り式といわれるもので、能率の上がらないものであったが、群馬県の富岡に出来た日本 最初の官営製糸工場などを見学して調べ、細島の生田長四郎らと協力して、60釜を備えるこの工場の実現にこぎつけた。長らく人手に頼っていた製糸が、機械 による製糸へと発展した。それは品質の改良・労働力の軽減・大量生産などの面で五箇山の「産業革命」ともいえるであろう。
明治15年 (1882)善治は、養蚕・製糸・機織りを一貫した作業にする計画を立てた。機織機械の購入に大きな資金を必要としたので、44ヶ村の共有資金からお金を 借りて設備を整えた。城端町から講師を招いて織機の技術を習い、この地方の絹織物業が盛んになるように尽力した。そのころ女の手仕事と言えば、麻の緒を紡 ぐことのほか無かったので、この機織は年と共に盛んになり大きな収入となった。
次に、善治は秋蚕の飼育に成功した。それまでの五箇山は、春蚕の 飼育だけしか行われていなかったのである。明治22年(1889)の7月、秋蚕の種紙を製造して、無料で分けて飼育させた。この成功によってそれからは春 蚕ばかりでなく、夏蚕と秋蚕と1年に3回飼育することが出来、繭の生産量は飛躍的に増え、その後、世界の景気に左右されながらも養蚕・製糸は五箇山産業の 中心となり、活気が見られるようになった。最盛期と言われる昭和13年(1938)に養蚕・製糸を生業とする家は、平村だけでも500戸を越えるように なった。
〈交通路を開くために〉
若い時代から全国を歩いた善治は、また、五箇山の交通路の開拓に命を懸けた人でもあった。
下梨から城端の町へ出るとき時は朴峠道を通った。下梨―梨谷―朴峠―横渡りー唐木峠―若杉、そして林道から東新田を通って城端別院前へ出るのが主要な道で あった。峠道としては、町出る1番近道であったが、冬は雪崩のために交通が途絶してしもうものであった。なかでも「横渡り」は難所であった。途中で雪崩に あったり、吹雪に巻かれたり、あわ(表層なだれ)に押し流されて人喰い谷の犠牲となることもあった。この難所をさけ、新しい道を造ることが、五箇山の人々 の願いであった。
明治16年(1883)、善治は、かねてからの計画を実行にうつした。村人の強い要望を担い県の協力を得て、ようやく道谷道路 の親切が親切が許可になった。梨谷から梨谷川沿いの道路を開き、細尾峠にいたり、細尾峠からは尾根ずたいに下りて、上田部落に達する道である。この道は経 費や労力の問題を乗り越えて、4年の歳月をかけ、明治20年(1887)に完成されたのであった。
この道の開通によって、雪崩の少ない城端往来 が確保できるようになった。昭和2年(1927)に城端・八幡間の自動車道路が開通するまでの40年間、五箇山と城端を結ぶ幹線道路として大勢の人が通 り、多くの荷物が運ばれることになった。かの有名な、郵便物を運ぶ「五箇山逓送隊」も、このルートを通ったのである。
また、善治は、大島から籠渡を経て、下出に至る小谷新道を開通させたり、下梨・大島間に初めて橋を架けることに成功したりした。それまでの五箇山には橋がなかった。
明治のはじめ、善治が架橋の考えを打ち明けたとき、村人の中には、成功の見込みがないと言う噂もあり、費用もなかなか集まらなかった。善治は詳しい計画の 元に、必ず橋を架けられるという信念を持って工事を初め、例え、目的が達成しなくてもその費用は自分の負担でやろうと覚悟して、人々の批判を気に留めない で仕事を進めた。明治8年(1875)、庄川をまたいで、下梨と大島を結ぶ鎖橋が初めて完成したのである。
〈強い信念の一生〉
このほか製紙業の奨励や学校の建築、さらに防疫などにも心を砕いて、一意五箇山の発展に尽くした。明治26年(1893)政府より「緑綬褒章」を贈られた。
明治31年(1898)4月28日、五箇山の発展に尽くした善治は、下梨の自宅で静かに71年の生涯を終えた。今、平村役場のある位置が、水上家の屋敷跡である。昭和30年善治の遺徳を忍び役場正面に胸像を建てた。
「その功績は白山の万年雪と共に、消え去らないであろう。」
松村謙三氏の筆による